難しい年頃の思春期の子育てで心がけたいことは?
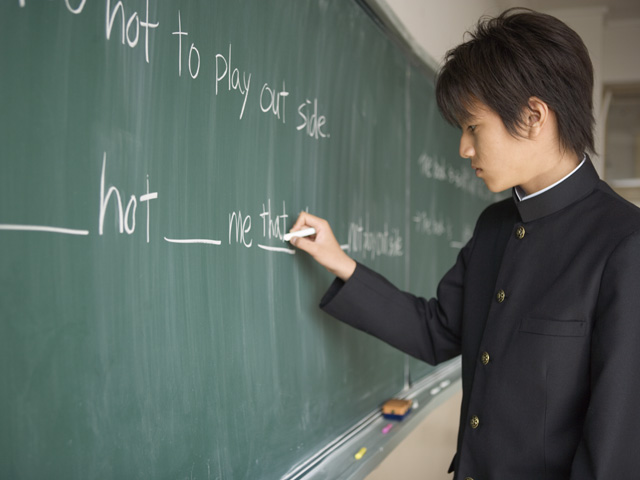
10代から中学生・高校生になると思春期で子育てが難しいと感じることも増えますね。
とくに情報過多の世の中で、何を信じればいいかわからない方も多いかもしれません。
子育て(とくに勉強や成績)について、20年以上たくさんのお子さんをみてきました。
難しい年頃の子育てについて3つのアドバイスを紹介します。
悩んでいる方の参考になれば幸いです。
1、言い方に気をつけ、共感
今年の春から入塾してきた子の一人が天然パーマです。
塾の授業中も、髪をまっすぐにしようとしているのか、しきりに髪の毛を引っ張っています。
彼は自分の髪についてコンプレックスを抱いているでしょう。
髪に気持ちがいくと、勉強する手が止まります。
時間ばかりが過ぎていき、なかなか学習課題が進みません。
学校の授業中も家でも集中できないと想像できます。
案の定、テスト結果は残念なものでした。
昭和の言い方はNG
私が子どもだった時代なら、先生も
「パーマ代が浮いていいじゃん」
「クルクルでかっこいいぞ」
「そんな小さいこと気にするな!」
などと軽口をたたき、笑い飛ばしたことでしょう。
しかし令和の子は、そんな言い方は傷つくかもしれません。
とにかく本人とできるだけ多く話して、理解してあげるように努めています
実際、学校で髪のことをイジってくる子がいるそうです。
髪はことはデリケートなことなので現在は親御さんと相談中です。
話を聞いて共感してあげて、塾が安心して勉強できる場になればと願っています。
思春期になると、子どもは容姿のことをとても気にかけます。
大人から見れば小さなことも、本人にとって重大な悩みであることも多いです。
悩みを軽く聞き流さず、共感して「大丈夫」と言ってあげましょう。
2、子どもに伴走する
ある部活動の子は、テスト直前の土日に練習試合が組まれていました。
私の塾はその土日にテスト勉強会をして、2日間で12時間勉強します。
その子は試合会場から18時に帰宅。
土日勉強会はまったく出られません。
試合を組む顧問も許す学校もどうかと思いますが、それ以上に、せっかくのチャンスを逃してしまうことに歯がゆさがあります。
しかし、こちらの都合で試合は中止になりません。
彼女の都合に合わせて、できるだけの勉強をするしかありません。
不登校=弱い子ではない
また、一時期不登校だった子も増えているようで、私の塾にも一人通うことになりました。
昔なら「やる気がない」「甘えている」などと、ひとくくりにされたでしょう。
しかし話を聞けば、起立性調節障害という、いわば病気だそうです。
学校や社会の不登校への対応も徐々に変化しているそうです。
部活動が激しい子、不登校の子、ネットを利用した通信高校を選択する子もいます。
いわゆる多様化が子どもたちにも進んでいると感じます。
昭和の常識を捨て、偏見の代わりに知識を得て、
子どもたちの変化にあわせて伴走しましょう。
お子さんが他の子と比べて「変わっているな」「特徴があるな」と感じたら、
他の子と同じにしようとすること以外に、一緒に伴走するのも一つの子育てです。
3、子育ての芯を持つ
受験についての情報があふれています。
ご近所さん、同級生、ネットやSNS。
知りたくて情報を求めるものの、過多な情報はかえって不安になります。
情報の中には、根も葉もないうわさや情報元のないデマも含まれています。
「うちの子にとっての幸せとは何か」を軸にご家庭の芯を持ちましょう。
そして、その芯を家族で共有しましょう。
価値観を共有していれば、何かを聞いたりするたびに不安や心配に襲われることは減ります。
「うちの子はうちのポリシーで育てる!」と決めて、自信をもちましょう。
勉強しない・反抗期の対応法

